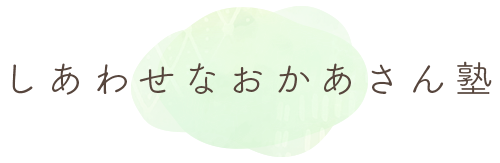「うちの子、どうして自分から勉強しないの?」その悩み、終わりにしませんか?
「宿題やったの?」「勉強しなさい!」
毎日同じことを繰り返しているうちに、親子でヘトヘトになっていませんか?
言われなければやらない我が子に、ため息をつきたくなる日もありますよね。
「どうしてうちの子は、自分から机に向かってくれないんだろう…」
そんなふうに感じている保護者の方は、決して少なくありません。
でも、安心してください。
子どもが自分から学び始めるきっかけは、ほんの少しの関わり方の工夫の中に隠されています。
今日は、ガミガミ言わなくても子どもが自然と学びたくなる、3つの大切なポイントをご紹介します。
自分から学ぶ子に育つ3つの秘訣
ポイント1:毎日の学習は「細切れ」でOK!
「勉強時間は、学年×15分が目安」
一度は耳にしたことがあるかもしれませんね。でも、特に小学校低学年のお子さんにとって、15分、30分とじっと座って集中するのは、実はとても難しいことなんです。
考えてみてください。私たち大人だって、40分間ずっと集中し続けるのは大変ですよね。
子どもの集中力は、もって5分から10分。それなら、その短い集中力を「逆手にとって」みましょう。
- 1年生(15分)なら… 5分 × 3回
- 2年生(30分)なら… 5分 × 6回
このように、短い学習をゲーム感覚で何度か繰り返すのです。
大切なのは、一気に長時間やることではなく、1日のトータルで目標時間を達成すること。この「短くても毎日続ける」という経験が、将来の長い学習時間の土台となっていきます。
ここで一つ、とても大切なお約束があります。
それは、勉強中に「怒る・叱る・ご褒美で釣る・ゲームを取り上げる」といったことをしないこと。これらは、子どもが勉強を「嫌い」になる一番の原因です。「ママやパパがいないと勉強しない子」になってしまう可能性もあるので、グッとこらえましょう。
ポイント2:「読解力」の前に「読みたい気持ち」を育む
すべての学力の基礎は「国語力」にある、と言われています。
だからこそ「本をたくさん読んでほしい」と願うのは、親として自然な気持ちですよね。
でも、ここで一番大切にしたいのは、「読解力」よりも、そのずっと手前にある「読みたい!」という気持ちです。そもそも本を手に取ろうと思えなければ、何も始まりません。
子どもたちの「読みたい!」という気持ちが、まるで泉のように湧き出てくるゴールデンタイムがあります。
それが、3歳から5歳くらいの「これなんて書いてあるの?」「読んで読んで!」とせがんでくる時期。
この大切なサインを見逃さず、「あとでね」と後回しにしないで、子どもの好奇心に付き合ってあげることが、将来の学力を大きく伸ばすカギになります。
「どんな本を読ませたら…?」と悩む必要はありません。
図鑑でも、お子さんの大好きなキャラクターが出てくる本でも、漫画でも大丈夫。極端な話、電話帳だっていいのです。
大切なのは、活字に親しみ、「読むって楽しい!」という体験をたくさんさせてあげることです。
ポイント3:世界を広げる「実体験」に勝る学びなし
特に10歳くらいまでのお子さんは、自分が実際に体験したことからしか、物事を具体的にイメージすることができません。
例えば、本の中に「田植え」という言葉が出てきても、実際に泥の感触や苗の柔らかさを知らなければ、その情景をリアルに思い描くのは難しいのです。
私たちはつい「何を学ばせるか」に目を向けがちですが、これからの時代に本当に大切なのは、「何を通して学ぶか」、つまり「自分で学ぶ力」そのものです。
だからこそ、お子さんの「好き」という気持ちを、どうか否定しないでください。
電車、危険生物、アイドル、漫画…。
大人の価値観で「そんなもの」と決めつけてしまうのは、とてももったいないことです。子どもの興味関心は、世界を広げ、学ぶ力を獲得するための最高の入り口なのです。
子育ては、親だけで頑張るものではありません。
地域の方や先生など、いろいろな大人と関わる中で、子どもは多様な価値観を吸収し、成長していきます。親である私たちがオープンな心でいることが、子どもの可能性を無限に広げることにつながります。
今日からできる、はじめの一歩
いかがでしたか?
「毎日学習」「読書」「実体験」。
どれも当たり前のように聞こえるかもしれませんが、その一つひとつに、子どもの学ぶ力を引き出す大切なヒントが隠されています。
完璧にやろうとしなくて大丈夫。
まずは今夜、お子さんの好きな本を「5分だけ」一緒に読んでみる。
週末に、いつもと違う公園までちょっと足を延ばしてみる。
そんな小さな一歩が、子どもの未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
毎日子育てを頑張っているあなたを、心から応援しています。