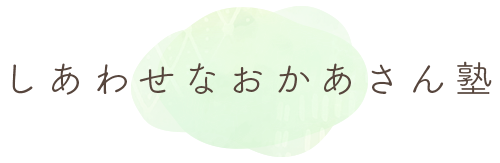「なんで、できないの?」足し算でつまずく我が子に、ついイライラしてしまうあなたへ
「9たす8は、いくつ?」「えーっと…」
小学校に入り、算数の勉強が本格的にスタート。お子さんが足し算の問題をなかなか解けずにいる姿を見て、「どうしてこんな簡単な計算に時間がかかるの?」と、ついイライラしてしまうこと、ありませんか?
私たち大人にとっては当たり前の足し算も、子どもたちにとっては人生で初めて出会う、大きな大きな壁なのかもしれません。そして、良かれと思ってかけてしまう「早くしなさい!」という言葉や、私たちの焦りが、実はお子さんの「算数、嫌いだな…」という気持ちを育ててしまっているとしたら…。
今日は、足し算でつまずくお子さんの心の中をそっと覗きながら、算数が「楽しい!」に変わる、私たち親にできる関わり方のヒントを探していきましょう。
理由1:そもそも「足し算」が、ピンときていない
私たち大人は、日々のお買い物などで「合わせる」「合計する」という経験を数えきれないほどしています。だから、「足し算」と聞けば、すぐにそのイメージが湧きますよね。
でも、子どもたちにとっては、おもちゃを「合わせる」という遊びの経験と、紙の上にある「+」という記号が、すぐには結びつかないのです。「簡単な問題なんだから、すぐに答えられて当たり前」という大人の思い込みこそが、親子双方のフラストレーションを生む最初の原因なのかもしれません。
【やってみよう!】
計算ドリルを開く前に、まずは生活の中で「合わせる」体験をたくさんさせてあげましょう。「テーブルの上のお皿と、キッチンにあるお皿、全部で何枚かな?」「赤いブロックと青いブロックを合わせると、いくつになる?」そんな具体的な体験こそが、足し算の本当の意味を教えてくれます。
理由2:計算の前に「数の感覚」が、まだ育っていない
足し算でつまずくお子さんは、計算そのものよりも、もっと手前の「数の感覚(数概念)」が曖昧な場合があります。
例えば、
- 数字の「6」を見て、りんごが6個ある状態をパッとイメージできるか?
- 「10」という数を、5と5、8と2、のように自在に分けたり、集めたりできるか?
特に「10の塊」を意識できるかどうかは、繰り上がりの計算をスムーズに理解するための、とても重要な土台になります。「9+8」を計算するとき、「8を1と7に分けて、まず9と1で10を作って、残りの7と合わせる」と考えられる力です。
大人にとっては当たり前のことですが、この感覚がお子さんの中にしっかりと根付いているか、遊びながらでいいので、もう一度優しく確認してあげることが大切です。
理由3:「早く、正しく」というプレッシャーを感じている
「簡単な問題は、早く、正確に解かなければいけない」
そんな無言のプレッシャーが、お子さんを焦らせ、本来持っている力を発揮できなくさせている可能性があります。
子どもたちの学ぶペースは、一人ひとり違います。すぐに理解できる子もいれば、じっくり時間をかけて、その分、確実な力として身につけていく子もいます。大切なのは、お子さんに「考える時間」をたっぷりと与え、すぐに答えが出なくても「大丈夫だよ」と認めてあげることです。
算数の勉強で、親が「怒ったり叱ったり」する必要は、まったくありません。むしろ、「早く解けるようになってほしい」と願うなら、「時間をかけてでもいいから、正確にやってごらん」と声をかけてあげることの方が、ずっと効果的なのです。
算数好きの種をまく、お母さん・お父さんの魔法
算数は「積み上げの教科」です。だからこそ、最初の段階でつまずいてしまうと、取り戻すのに大きなエネルギーが必要になります。
一番大切なのは、難しい問題を解かせることではありません。
「できた!」という小さな成功体験を、見逃さずに褒めてあげることです。
「わかった!」「すごいね!」「さすがだね!」
そんな肯定的な言葉のシャワーが、お子さんの心に「算数って、楽しいかも」「自分は、できるんだ!」という自信の種をまき、さらに難しい問題にも挑戦してみようという意欲を育てます。
足し算のつまずきは、お子さんの能力の問題では決してありません。計算の速さよりも、生活の中にあるたくさんの「楽しい!」や「分かった!」という本物の体験を、どうか大切にしてあげてください。
お母さん、お父さんの「待ってあげる優しさ」と「できたね!の笑顔」が、お子さんにとって最高の栄養になります。今日の「ゆっくり、じっくり」が、未来の学びを支える、大きくて丈夫な根っこを育てていくはずですよ。